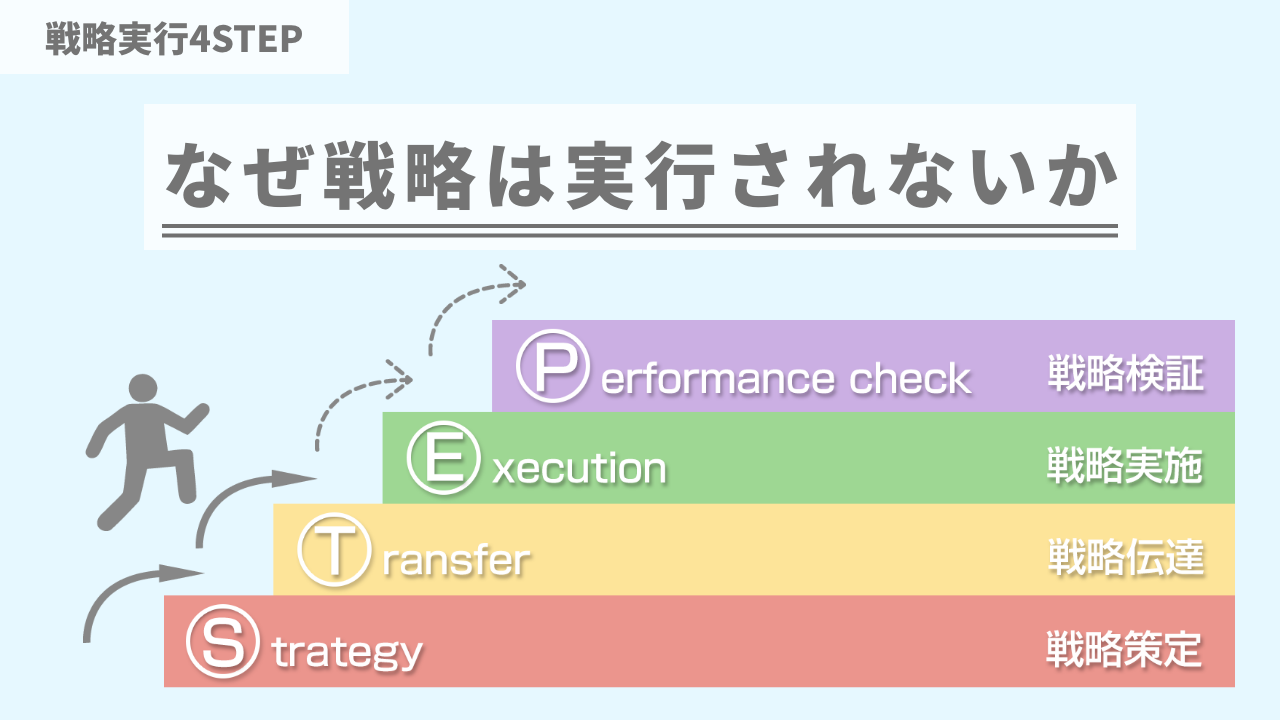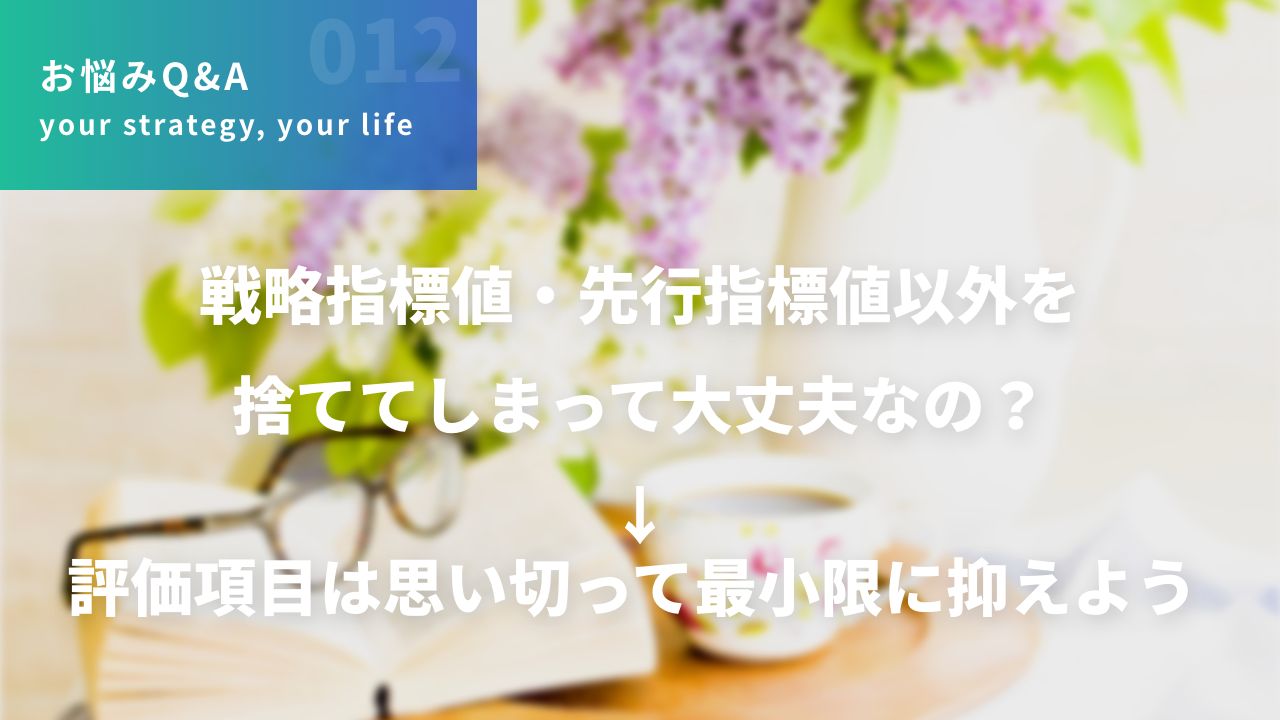【第2話】電子書籍ってどうなの

次の日、吉川社長は社内の幹部に召集をかけた。編集長の木村、営業部長の鈴木、管理部長の佐藤の3名が社長室に集まった。突然の召集に彼らは緊張ぎみだ。3名とも社歴は自分よりもはるかに長いので、吉川社長は互いの感覚が違うことに遠慮して、あまり管理職連中を呼びつけることはなかった。しかし、そんなことも言ってられない。
「新しい事業を始めようと思う。電子書籍を作りたい。」
3名の幹部は、少々安堵した。会社の経営状態が厳しいことは皆知っている。あらたまって社長に呼ばれるということは、もっと厳しい話、たとえば、リストラとか資金ショートとかを覚悟していたのだ。
国内の出版社は4000社ほどあり、業界全体の売上規模は2兆円ほどだったが、最近はそれを割り込み、減少傾向に歯止めがかからない。そして、規模の大きな企業は数えるほどで、大部分は小規模な企業である。超時空社も社員20名ほどの小さな会社である。
従来、「出版社」、「書店」、そして両者をつなぐ流通の機能をもつ「取次」が一体になって、本を読者に届けるという安定体制を構築していた。しかし、若年層を中心とした本離れ、書籍のネット販売、新古書店の台頭など、出版業界を取り巻く環境の変化は激しい。街の書店や、超時空社のような中小規模の出版社では、倒産や廃業するところも増えてきているのが現状である。
そんな中、吉川社長は、会社の業績低迷の状況と、新事業として電子書籍プロジェクト着手の必要性を説いた。電子書籍はアメリカでは普及が進んでいるが、日本では状況が異なる。これまで、何度も電子書籍元年というキャッチフレーズで、「これからは紙の書籍はなくなる」などと言われることもあったが、電子書籍コンテンツの不足、慣れないと煩雑な書籍購入手順などもあって、日本では十分に普及しているとは言えないのが現状だ。
しかし、ここ10年ほどで、スマホ・タブレット型端末の進化やコンテンツの拡充などが進み、今度こそ電子書籍が本格的に普及するのではという声が大きくなっていた。
多くの中小出版社の例にもれず、超時空社の幹部社員たちは、あまり技術に詳しくなく、これまで電子書籍への取り組みを後回しにしていたが、もはや避けては通れそうにない。
また、昨年入社した、元大手電機メーカーのエンジニアの野中であればなんとかしてくれるかもしれないという淡い期待もあって、今回、取り組んでみることにした。
「野中さんは技術的なことはわかるかもしれませんが、編集部員は必要ありませんか?」
木村編集長は吉川社長にたずねた。
一瞬の間をおいて吉川社長が口を開いた。
「思い切って、うちで一番若い社員はどうかな。」
「誰でしたか…… 最近、新入社員入ってないから……」と鈴木営業部長。
「一番若い社員…… 編集2課の秋山みのりですか? できますかね……」と木村編集長は不安そうだ。
「確かに未知数ではある。しかし、彼女は、私が社長になってから唯一新卒で採用した社員だ。彼女の可能性にかけてみたい。」
超時空社は電子書籍をつくることを決定した。
しかし、この会議の出席者で電子書籍を購入したことがあるのは、吉川社長だけだった。
**********
その日、みのりは、久保に半ば強引に連れてこられた神保町のK書店で、陳列の手伝いをしていた。
久保は、勤続25年のベテラン営業部員だ。出版業界の景気がよかったころの話を、よく大きな声でしゃべっている。席は編集部からは少し離れているが、みのりのところでも十分に聞き取れるほどだ。仕事をすればするほど儲かる時代を過ごしてきた経験もあり、残業はいとわない。みのりのことは、ひよっこのお嬢さん扱いだが、実は気にいっているようで、勝手に、自分のアシスタントのように使っている。
出版社は自社の書籍を、直接、書店に販売するわけではなく、書籍の問屋といえる「取次」を経由して書店に書籍を提供する。書店側は、取次から提供された書籍のうち、売れそうな書籍を店頭に陳列する。ということは、店頭に陳列しない書籍もあるわけだ。
店舗のスペースは限りがあるので並べない書籍が発生することはやむを得ないが、実は、書店にとっては、初めから並べる気がないような書籍も存在する。
並べなければ売れ残って困るだろうと思うかもしれないが、売れなくても書店は困らない。売れなかった書籍は再び取次を経由して出版社に返本できるのだ。だから、取次から送られてきた書籍を、開けもせずに、そのまま返本することもあるくらいだ。
一方、出版社にとっては、売れ残りはそのまま在庫となってしまうので、久保のような出版社の営業マンとしては、自社の書籍を並べてほしい、それもできるだけ目立つところに並べてほしいわけである。そこで、自社の書籍をいい場所に並べさせてもらうかわりに、陳列の手伝いをしているのである。
久保が、陳列の手を休めて、まわりを見渡すと、みのりの姿が見えない。
「あいつ、また、さぼってんのか……」
とつぶやきながら、久保は新刊コーナーの陳列を終えた。
店長を探しに、店の奥のほうへ行くと、トイレのほうからみのりの声が聞こえてきた。
「はい、すぐに送ります。」
「よろしくお願いいたします!」
電話に集中しているのか、久保には気づいていないようだ。
「あいつは、まったく……」
久保が舌打ちしていると、店長が出てきた。
「ああ、久保さん、終わりましたか。」
「はい。」
「ありがとうございます。今度の新刊、当店でもプッシュしますね。ところで、超時空社さんでは、電子書籍は出されないんですか?」
「えっ、電子書籍ですか?今のところやってないですよ。手軽さでは紙の本にはかないませんよ。若い人はわかりませんが、我々世代だと、やはり紙じゃないでしょうか。」
「そうですか。実は、私、最近、電子書籍端末を買ったんですよ。」
「えっ、そうなんですか?」
「うちは古い木造の家なんですが、これ以上本が増えたら、本の重さで床が抜けるんじゃないかって前から不安でしてね。最近は妻が地震の時に怖いから少し処分してくれって言うようになって。で、思い切って、これからは電子書籍も併用して、紙の本を整理しようと思いまして。」
「そうでしたか。」
電子書籍対応で後手に回っている超時空社の痛いところをつかれて、久保が少々困惑していると、みのりが何食わぬ顔をして戻ってきた。苦々しく思いながらも、ちょうどいいタイミングと思った久保は、K書店を辞することにした。
「秋山、どこ行ってたんだ。帰るぞ。」
「あっ、はい。」
K書店を出た久保は、みのりに言った。
「秋山は電子書籍って使ってるか?」
「えっ、電子書籍ですか?一度も触ったことないです。」 あっけらかんというみのりを見て、久保は、やれやれという顔をして、地下鉄の駅に向かった。
つづく
はじめから読む

ユアスト 江村さん
第1話は下記より御覧ください。
【第1話】超時空社