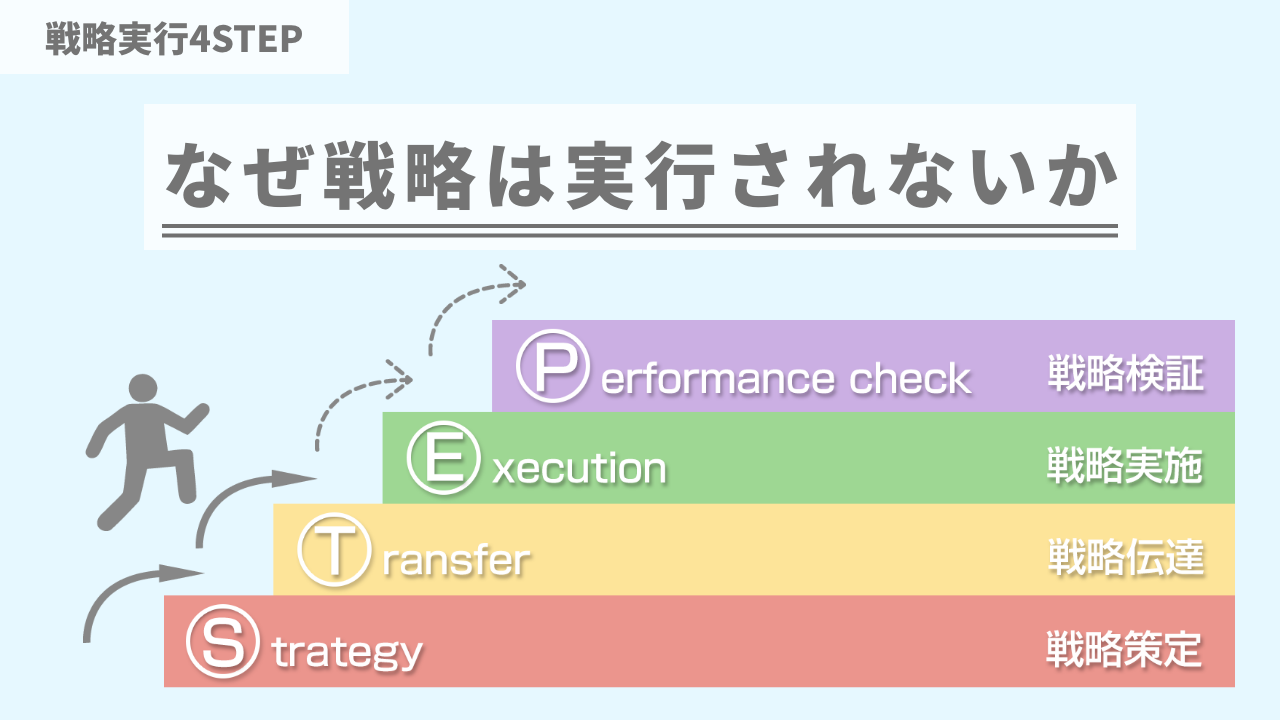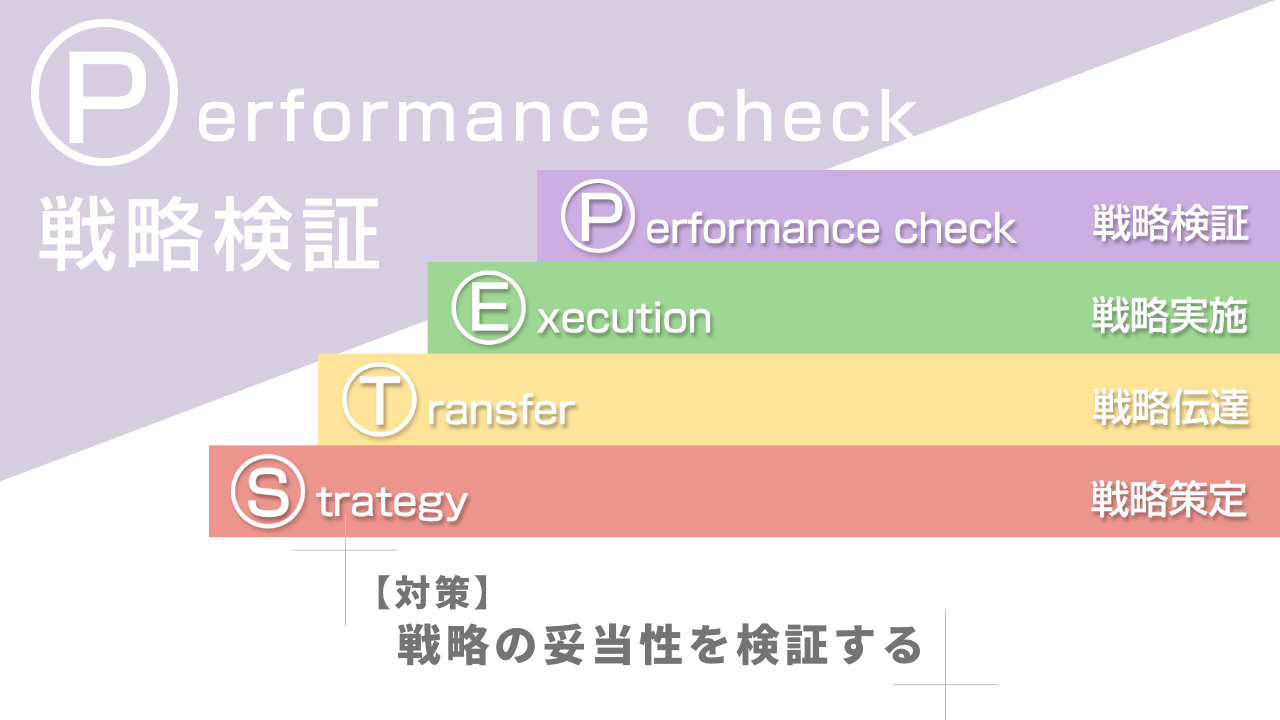【第1話】超時空社

夕日が沈む。
そのとき、社長の吉川は富士見ビルの屋上でひとり箒を握りしめ、ビルの隙間から富士山を眺めていた。吉川は気持ちがもやもやとすると、箒を持ち出してビルの掃除をしてしまう。
富士山といっても、5階建てのビルの屋上から見えるのは、高いビルやマンションにところどころを隠され、モザイクのかかったようないびつな富士山だ。それでも辛うじて隙間から「見える」のは、ここが東京のど真ん中だということを考えれば、奇跡だと思う。
奇跡といえば、自分が経営している超時空社が、まだ出版社として存続しているのも奇跡かもしれない。
超時空社を作ったのは吉川の父親である。歴史ものや紀行ものなどを中心に多くの文学作品を手掛けてきた。以前は、文学賞にノミネートされる作品もあったが、最近ではヒット作にも恵まれず、売上の落ち込みが激しい。売上を確保しようと、静岡出身だった父は人脈を生かして、静岡県内のタウン誌の編集などにも手をひろげてきたが、逆に手を広げすぎてしまい、忙しいわりに会社の経営状態は全くよくならない。当然ながら、社員のモチベーションも停滞気味である。
超時空社という変わった名前は、「読書によって時間を超えた想像上の旅を提供したい」ということで父親が名づけた。 5年前、父親が急に体調を崩し、仕事を続けることができなくなったとき、吉川は勤めていた大手旅行会社を退職して、社長を引き継いだ。吉川は父が築いてきたものを守りたいと思った。そして、父とともに仕事をしてきてくれた社員とその家族の生活を守りたかった。大きな決断ではあったが、自身も本好きということもあり、その決断をするまでに吉川に迷いはなかった。
しかし、出版業界を取り巻く環境は非常に厳しく、このままではじり貧である。父や、社員たちのためにも、めいっぱいあがいて、やれることをしたい。
よし、決めた。
この間から迷っていた新事業をやってみよう。 誰が適任かも迷っていたが、ここは思い切って一番若い社員を抜擢してみよう。自分が社長としてこの会社に来てから、唯一新卒で採用した社員の可能性にかけてみよう。
**********
日が暮れる。
そのとき、秋山みのりは走っていた。
これからが私の一日の本番。これからが本気を出すところ。今日は英会話スクールだ。
普通、みのりのような編集者に、スクールに通う時間などない。しかし、みのりは毎週のようにフラワーアレンジメント、スキルアップセミナーなどと、予定をいれている。毎回同じ曜日の夕方「取材行ってきま~す」と会社を逃げ出す。
今日は運悪く営業部の久保につかまってしまった。
「おい、俺が頼んどいた新刊の販促資料できてるか?」
「え?あれ、来週まででしょう?まだです」
「早くしてくれ。明日お客さんのところへ持っていくから今日中に欲しい」
「え~!そんなこと言われても、私にだって予定が……(せめてもっと早く言ってよ!)」
「とにかく頼んだからな」
久保は声が大きく、いつも一方的に言い負かされてしまう。で、なんとか久保の仕事はやっつけて、メール添付でエイッと送ると、そのまま声もかけずに退社した。 だいたい、なんで私は営業部の資料づくりばっかりしているんだろう。みのりの名刺には、
超時空社
編集部
秋山みのり
と書いてあるが、自分が本当に編集者かと聞かれたら、イマイチ自信が無い。読者の想像をかきたてるような書籍を企画したいと思い、大手出版社への就職を希望していたが叶わず、第一志望ではなかった超時空社に入って4年目。小さな出版社に新卒の社員はめったに入らない。超時空社でみのりはいまだに一番若い社員だ。新しい経験をさせてやるという名目で、あちこちの部署から半端な仕事の手伝いに駆り出される(と、みのりは思っている)。
子供のときから本が大好きなみのりにとって、あこがれの仕事に就いたはずなんだけど、現実は違った。中小の出版社でも、それなりにおもしろい企画をたてられると思っていたが、毎日の仕事はタウン誌の編集と、雑用ばかり。会社から本当に必要とされている感じもしない。
せめて、後輩ほしいな~。で、一緒にグチりたい。 前に向かって走りながら、心は後ろ向きなみのりであった。
**********
夜が訪れる。
そのとき、野中はため息をついた。
とりあえず、与えられたことをやるしかないかな。
やっと決まった仕事だし、まだ一年経ってないし。
会社が小さいと、これからのキャリア相談とかしてくれる部署もないし。そもそも出版社で情報システム担当のキャリア相談しても、わかる人いないだろ。
野中は現在47歳。一年前までは、大手電機メーカーに映像技術関係のエンジニアとして勤めていたが、所属していた事業部自体が会社の方針転換でなくなり、早期退職制度を利用して仕事をやめた。超時空社に転職してからは、社内の情報システムの管理を手掛けている。
まったく違う世界に飛び込んで、新しい人生を始めようと思っていたが、それは決して輝きに満ちたものではなかった。家庭の生活を充実させようと思ったが、それも難しい。残業続きだった以前と比べれば家に帰るのは早くなったが、もはや子供達は成長して大学生となり、バイトやサークルと自分の世界に夢中だ。
すると、家で妻と二人きりの時間が増える。これはこれで困る。何を話したらいいかわからない。そんなわけで、野中は自宅の最寄り駅よりも3つ手前の駅で降りると、一時間かけてゆるゆると家まで歩くのだった。
**********
月が高く上ったころ、みのりは、英会話スクールでのレッスンを終えて、自宅の最寄り駅まで戻り、駅近くのカフェに寄った。英会話スクールは会社と違って、学生など、自分より年下の人が多く、和気あいあいとした雰囲気である。そのため、社会人の先輩として、就職に関する相談を受けることも多いのだが、自分自身があまり仕事で結果を出せていないので、返答に窮することもある。
軽い夕食をとった後、みのりは、一心不乱にスマホの画面を見つめていた。そこには、「新規事業立ち上げため編集者若干名募集」という大手出版社の求人情報が表示されていた。
つづく

ユアスト 江村さん
現状をかえたい。何か変えたい。だけど、どうしたらいいかわからない。何かしなければと思う。
どうしたら、もっとおもしろく働けるんだろう。
そんなアナタを応援する物語です。